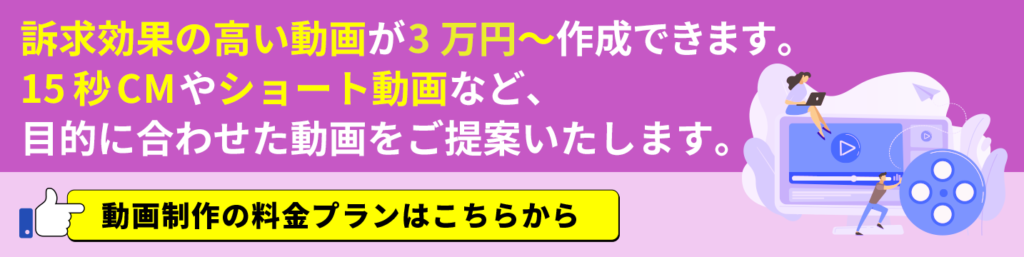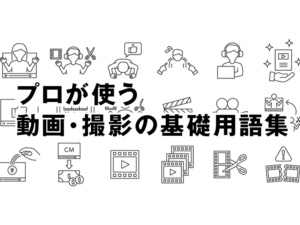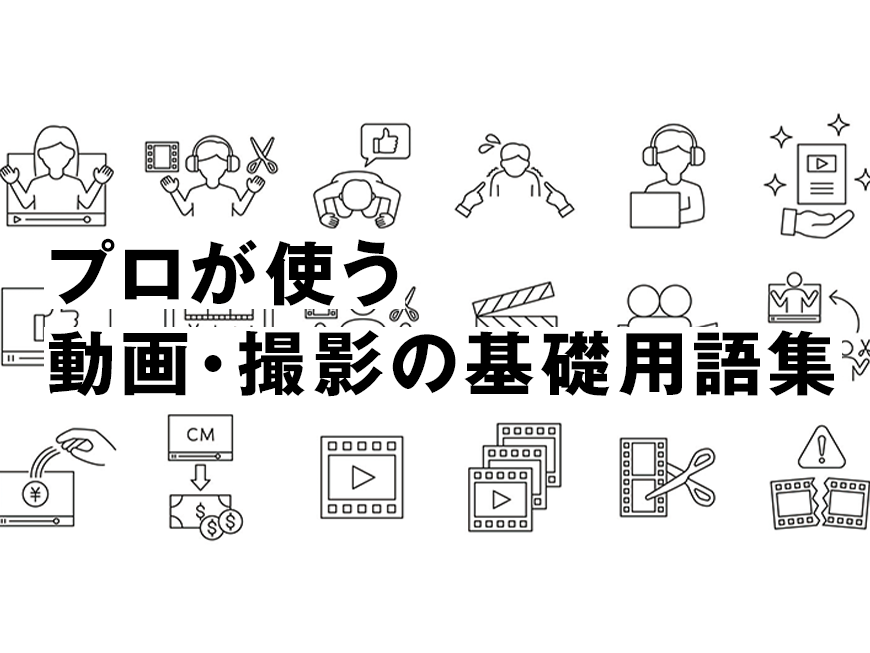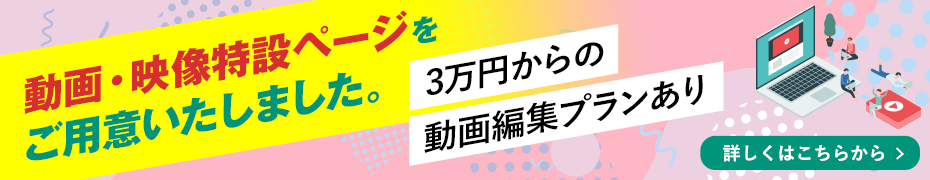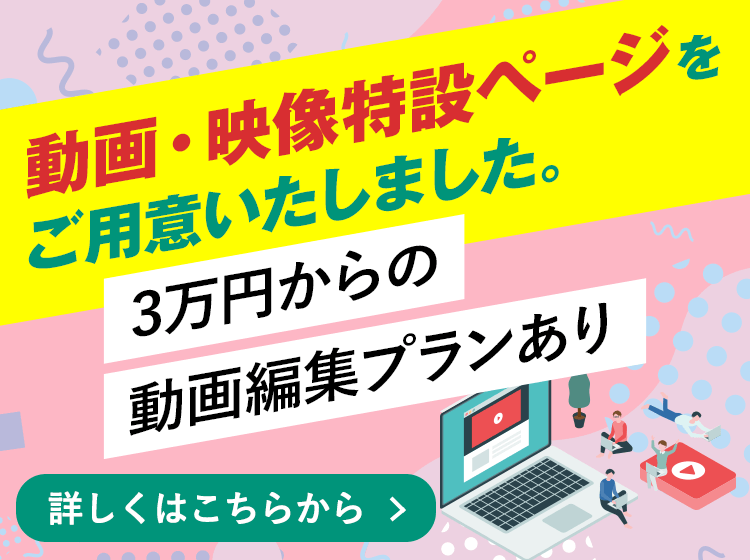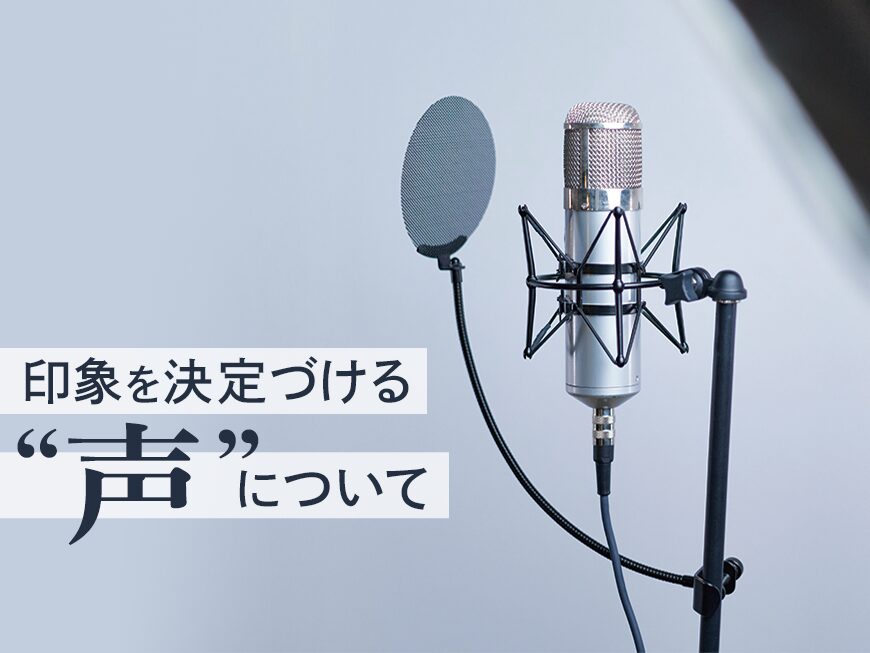
テレビ番組やネットの配信動画などを見た後で、ある特定の言葉がずっと頭に引っかかっていたり、頭の中に流れるメロディをふと口ずさんでいたりといった経験はありませんか?
映像と共に流れるBGMや、動画の中で発せられるセリフなどの「音声」は、意外と記憶に残るものです。特に自分が今関心を持っていることに関する内容やインパクトのある言葉、耳障りの良いセリフなどが聞こえてくると、たとえ「ながら見」で流していた動画でも、つい映像を注視してしまうことも。
ただし、人間の記憶容量は限られているため、すべての内容をずっと覚えていられるわけではありません。となると、広告動画を見た視聴者に、その中に出てきた商品やサービスを記憶してもらうには、どのような音声を使った動画を作るのが良いのでしょうか。
今回は特に「ナレーション」という観点から、動画の中で音声がどのような役割を果たしているのかを、わかりやすく説明いたします。
ナレーションが動画に与える影響や、どのようなナレーションがより効果的なのかについて解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
【関連記事】
>動画の「編集のみ」を外部に依頼するには?流れやコストを徹底比較!
>【プロが解説】動画・映像制作における必須の用語集
目次
1.そもそも「ナレーション」とは?

日常よく耳にする「ナレーション」という言葉ですが、そもそもどういう意味があるのかご存じでしょうか?「精選版 日本国語大辞典」では、次のように説明されています。
| 1.物語ること。叙述。話術。話法。[初出の実例]「此種の文章今小別して三となす、曰く叙文(ナルレイション) 万事の歴由を記する文」(出典:修辞及華文(1879)〈菊池大麓訳〉通知) 2.ラジオ番組の話の部分。また、映画・テレビ・演劇などで、場面の進行に応じて解説を加える場面外の声。語り。 |
企業などが視聴者に向けて作るPR動画などの場合は、2の意味で用いられています。つまり、「声のプロであるナレーターや声優に、動画のストーリーやメッセージを語ってもらう表現方法」だと言えるでしょう。ちなみにメディア業界内では、「NA」や「ナレ」といった略語を使う場合もあります。
2.ナレーションは動画に必須なのか?

動画を制作する際、ナレーションは必ず入れる必要があるのでしょうか。映像や音楽だけでは、動画は成立しないのでしょうか。
結論から言うと、ナレーションは入れるべきだと考えます。もちろん、ナレーションを使わずに、映像とBGM、そしてテロップを流すだけでも動画としては成立します。
しかしながら、「視聴者に的確な情報を届けて記憶にとどめてもらう」という動画の目的から言えば、やはりナレーションは必要です。ここではその理由を3つ説明していきます。
「映像と音声との組み合わせ」で動画の効果が高まる
動画の持つ大きな特徴に、「情報量の多さ」があります。映像と音声、つまり視覚と聴覚の両方から入って来る情報があるからこそ、動画は視聴者に多くの情報を伝えられるのです。
この2つの要素で構成されて初めて、映像を「動画作品」と呼ぶことが可能になります。つまりそれほどまでに、ナレーションを含めた音声は動画にとって重要だと言えるでしょう。
言い換えれば、特に視聴者に内容をしっかり届けたい場合、その動画の良し悪しはナレーションで決まると言っても過言ではありません。
ナレーションを入れる際は、後述する原稿の作成方法や外注する際の注意点を参考に、目的に合った方法を検討しましょう。
ナレーションの使用で訴求力を高められる
どんなナレーションを入れるかによって、動画の印象は劇的に変わってきます。その企画の目的やターゲット、さらには動画の中で語られるストーリーなどにより、どんなナレーションがふさわしいかを考えなくてはなりません。
一口にナレーションと言っても、その演出方法には様々なバリエーションがあります。そのいくつかを、例を挙げてご紹介しましょう。
・抑揚をつけず、説明的に淡々と語っていく
自社の商品やサービスの紹介、製品の使用方法など、視聴者に情報を正確に伝える動画に向いている方法です。
・感情をこめて、視聴者の心を揺さぶるように表現
視聴者の感情に訴えることで、自社のブランドを強く印象付け、企業と消費者とのつながりの強化を図ります。
・親しみやすい、ユーモラスな演出で語りかける
具体的には、ある地域特有の方言を使うなど、動画にエンターテインメント的な要素を加える方法が考えられます。そうすることで視聴者に親しみやすい印象を与え、商品やサービス、そして企業自体にも親近感を抱いてもらいやすくなるでしょう。
また、動画の目的に合ったナレーションの表現方法をうまく駆使できれば、映像自体が持つ視覚的な情報に加えて、ナレーションによる独立したメッセージを提供することも可能です。
例えば視聴者が画面から目を離していても、耳から聞こえてくる音声が魅力的な内容なら、動画の内容に興味を持ってもらえる可能性が高くなります。
動画の内容に対する補完的な役割が期待できる
ドラマや映画に出てくる会話の場面で、登場人物の行動を説明したり、その気持ちを代弁したりするナレーションが、補完的に挿入されるシーンを見た経験はないでしょうか。
インタビュー動画やショートドラマなどでは、実際に本人の口から語られている内容を補完する役割で、ナレーションを用いる場合もあるのです。インタビューや会話の内容がわかりづらい時、ナレーションが入るとすっきり理解できることも。
また、映像に登場する人物や話題の相関関係について補足したり、画面に表示されるグラフや図表、数字についてわかりやすく説明したりするのも、ナレーションの役割だと言えるでしょう。
3.ナレーションで気をつけなくてはならないこと

動画にナレーションを入れる場合、その原稿はどのように作られていくのでしょうか。ここではナレーション原稿を作る際に注意すべき点や、原稿作成のコツについて解説していきます。
正しい日本語で表記する
そもそも「正しい日本語」とは何でしょうか。「文法的に正しい」「用法的に正しい」「意味的に正しい」など、言葉を用いる際には様々な「正しさ」が求められます。
ナレーションに求められる「正しい日本語」とは、主語と述語、修飾語などそれぞれの関係性が正しく呼応していることや、用語の意味を正しく理解できていることを意味します。
「この言葉の意味や使い方は合っているのか?」「この用語で正確に言いたいことが伝わるのか?」といった点をしっかり確認することで、後々のトラブル防止にもつながるからです。
とは言え、文法的には正しくても、日常の中で見たり聞いたりした場合、違和感のある表現も存在します。また、言葉は生き物だと言われますが、時代により意味や用法が変わってくることも珍しくありません。
よく引き合いに出されるものに、「ら抜き言葉」が挙げられます。また、「大丈夫」が断りの意味で使われたり、「全然」が肯定の意味で用いられたりするのも、最近の風潮だと言えるでしょう。
実は後者は誤用というわけではないそうですが、特に年配の方の中には、違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。
一度ナレーションに違和感を覚えると、それ以降の内容が頭に入って来なくなります。視聴者の離脱を防ぐためにも、特定の年代や業界以外では馴染みのない用語や表現は、なるべくなら避けるべきでしょう。
ここで注意すべきなのは、人が作る原稿には、作成者に特有の言い回しや文体のクセ、間違って覚えている表現、そして思い込みや価値観が出てしまいがちな点です。
これは作成者の年齢や性別による場合もあり、本人が自覚していないケースも多いため、必ず様々な年代や性別の第三者にチェックしてもらうようにしましょう。
聞き間違いがないように簡単な言葉で言い換える
音楽や映画を鑑賞している場合はともかく、動画の視聴者は「ながら」で見ていることも多いもの。聞き取りにくかったり、聞き間違いやすかったりする言葉の使用は、できるだけ避けるべきでしょう。
最初から最後まで集中して動画を見ている人は、実は多くありません。視聴者が画面を見ていない状態でも、ナレーションが耳に入った際、意味がスッと通じる言葉を選ぶのが望ましいのです。
そのためには、一つひとつの文章をなるべく短くすることも重要です。リズムが良く、耳障りも良い言葉を丁寧にチョイスしながら作っていきましょう。
また、目で文字を追って読む場合と、耳で音として聞く場合では、同じ文章でも理解のしやすさが違うことがあります。原稿が書き上がったら、必ず声に出して何度も読んでみるようにしましょう。
動画の表現方法やイメージに合わせる
動画を制作する際は、まず目的やターゲットなどをしっかりと定めた上で、具体的な内容や構成を考えていくと思います。
ナレーションを入れる際も同様です。動画の目的やターゲットを理解した上で、映像のテンポ感やテンションに合わせ、それぞれの動画に最適な表現方法を考える必要があるのです。
例えば、商品などの使い方を説明したマニュアル動画を作る際は、視聴者を煽るような演出は逆効果です。テンポが早くテンションが高いナレーションでは、説明が頭に入って来ない可能性も。
マニュアル動画の目的は、視聴者にわかりやすく説明し、しっかりと理解してもらうことです。この場合はテンションは控えめにして、ゆっくりと落ち着いた口調のナレーションを入れるのが正解です。
ナレーションと一口に言ってもその種類は実に多様であり、動画の内容によって適切な表現方法も変わってきます。
・やわらかい女性の声が良いのか、落ち着いた男性の声が向いているのか。
・口語で話しかけるべきか、文語調で説明すべきか。
・抑揚は抑えた方が良いのか、ドラマチックに感情を込めるべきか。
それぞれの手法や声の特性を理解し、活かした上で、動画に合ったナレーションをつけるようにしましょう。
4.ナレーションを収録する3つの方法

ナレーションを入れる工程は、動画の出来栄えを左右する、大詰めの大切な作業です。そのため、ここをいい加減に進めてしまうと、完成した動画全体に違和感が生じてしまうことも。
自社でも入れられないことはありませんが、動画のクオリティを確保するには、やはりプロに依頼するのがおすすめです。ここではナレーションを入れる方法を3つご紹介します。
プロの声優・ナレーターに依頼する場合
声優やナレーターは、言わば「声」を扱うその道のプロです。映像に合わせ、絶妙な間を取ったり抑揚をつけたりといった、プロならではのテクニックや表現方法を最大限に生かした収録ができます。
動画を制作するにあたって、特段の制約や指定がないのであれば、プロの声優やナレーターに依頼するのがおすすめです。
また、ナレーションの制作を外部に頼む場合は、動画制作会社やナレーション制作会社、あるいはフリーランスなどに依頼するといった方法があります。
流れとしては、動画の内容や原稿に合った声色やテンションなど、希望するナレーションのイメージをしっかりと伝え、用意した原稿を渡して実際の収録に臨みます。
動画制作会社に依頼すれば、プロの目線でナレーション原稿の作成からナレーターの提案・選定、そして収録までワンストップで行ってくれるので、一番手間がかからず安心な方法だと言えるでしょう。
AIによる音声を利用する場合
最近はナレーション業界にも、AIの波が訪れています。AI音声技術の発達により、文字を入力するだけで、人間に近い、自然なナレーション音声の出力が可能になってきました。
かつては棒読みのイメージがあったAIも、今では豊かな感情表現が可能になっています。ボイスチェンジャーや多言語対応も容易なため、今後はますますAIを利用する機会が増えていくでしょう。また、コストや納期の面でも、AIの活用には大きなメリットが期待できます。
しかしながら、現時点ではやはりAIは機械であり、より人間らしい感情の表現が求められるナレーションの場合は、不自然さがぬぐえないことも。
逆に言えば、感情表現を要しない動画、例えばマニュアルの説明動画や社内研修用の動画などであれば、AIによる音声でも問題はないと思われます。目的に応じて使い分けてみるのもいいかもしれません。
自社・自分で収録する場合
何らかの事情で、ナレーションを外部に委託できないケースでは、自社や自分でナレーションの収録を行うことになります。
その場合、録音機材を新たに揃える必要があるかもしれません。もちろん、パソコンやスマホでも録音自体はできますが、音質が悪かったりノイズが入ったりと、どうしても品質が気になります。
商品やサービス、ブランドのプロモーションといった、クオリティを求められる動画を制作するのであれば、自社や自分での収録はせずに、プロの制作会社に依頼することをおすすめします。
まとめ:動画の出来を左右するナレーションの収録は、映像と等しく重要なプロセス
ここまで、動画のナレーションについて説明してまいりました。動画制作と聞くと、映像の撮影や編集にばかり気を取られがちですが、ナレーションの収録も重要なプロセスだということを忘れてはなりません。
映像の内容とまるで合っていないナレーションを入れると、視聴者に違和感を与えてしまい、動画の内容が印象に残らなかったり、視聴離脱を起こしたりといった結果になりかねないからです。
動画の目的やターゲットに応じて、どのようなナレーションが良いのか、どのようなナレーターに依頼したらいいのかを、今回の記事を参考にぜひ考えてみてはいかがでしょうか。
記事の中でもお伝えした通り、動画という媒体のメリットを最大限に発揮させるには、映像だけではなく、ナレーションを含めた音声を入れたほうが効果的です。ぜひプロの声優やナレーターに依頼して、視聴者の記憶に残る魅力的な動画制作を目指しましょう。
バドインターナショナルでは、ナレーションの制作も、動画・映像制作会社としてワンストップで対応いたします。
動画撮影からイラスト・アニメーションなどの制作・編集、キャスティング、ナレーション原稿の作成からナレーションの収録まで、ご依頼から完成・納品まですべての工程で対応が可能です。
「これから動画を作りたいが、まだ具体的なイメージができていない」といった場合でも、ぜひお気軽にご相談ください。
※「おすすめの動画制作・映像制作会社を一挙公開!」として、弊社が掲載されました。
詳しくはこちらをご覧ください。