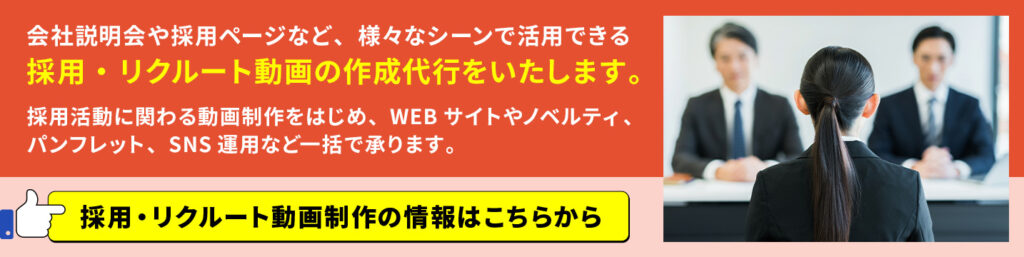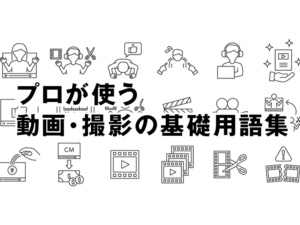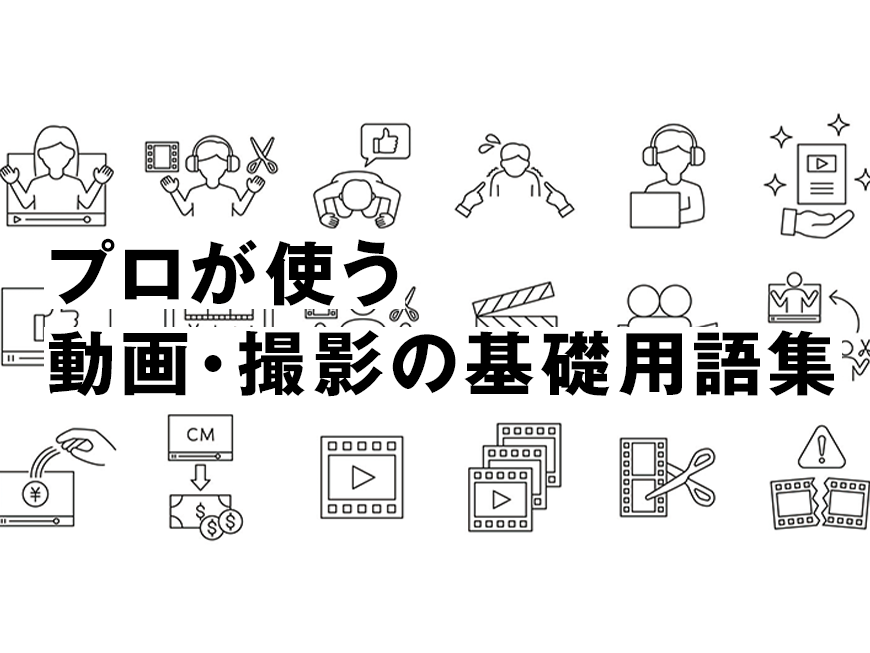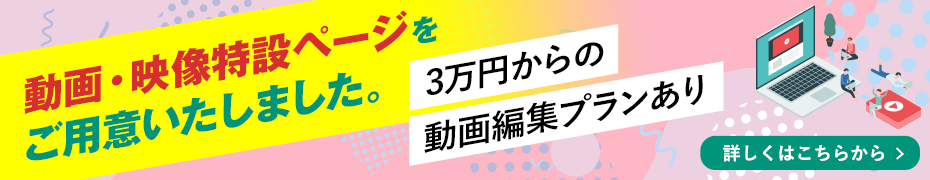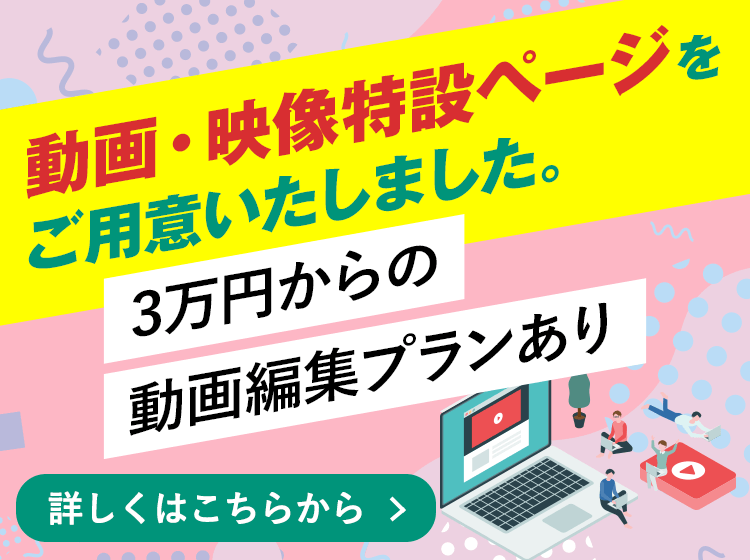「求人を出しても、なかなか人が集まらない」
「採用してもすぐに辞めてしまう」
企業の人事担当者は、こんな採用の課題に常に頭を悩ませているのではないでしょうか。
少子高齢化が進み、労働人口が減少している現代においては、人材獲得は多くの企業にとって大きな問題であるとともに、日本の社会全体が持つ課題でもあります。
特に中小企業の場合、大企業に比べ知名度や待遇の面でどうしても劣るため、人材獲得に苦労しているという声もよく聞かれます。
そこでおすすめしたいのが、「採用動画」の活用です。採用活動を動画を使って行うことで、中小企業でも十分に優秀な人材の獲得に繋がる可能性があるのです。
今回の記事では、採用動画制作のコツや現在のトレンド、そして最大限に活用するための効果的な方法までを網羅して解説いたします。ぜひ本コラムを参考に、採用戦略に動画を取り入れてみてください。
【関連記事】
>ディレクターが唸った!採用動画の事例15選!気になる費用も解説します。
>採用動画でミスマッチを減らす!制作のポイントは「求職者目線」を忘れないこと!
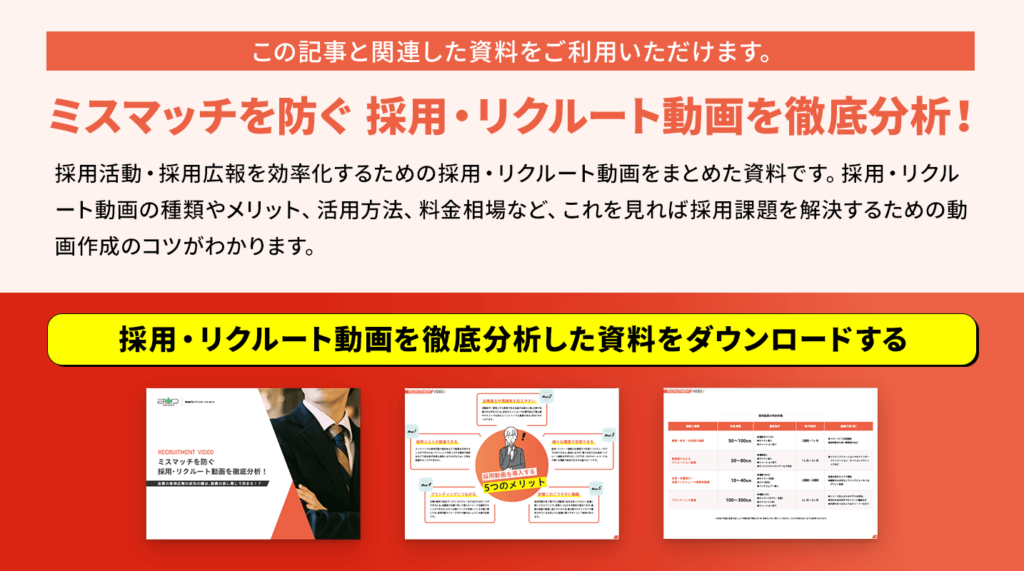
目次
1.採用動画を導入すべき3つの理由

前述の通り、今日の労働市場には人材不足やワークスタイルの多様化といった、人事担当者の頭を悩ませる課題が山積しています。
採用戦略を考えるにあたり、どの企業も求職者への様々なアプローチを模索し、計画・実践しているでしょう。その中でも動画コンテンツは、重要な施策の一つとなるはずです。
有効な採用動画を1本用意できれば、それが採用活動の課題を解決するための突破口になる可能性もあります。
ここでは採用活動における動画の活用がなぜ効果的なのか、その理由を3つご紹介します。
企業の魅力を伝えられる
採用動画の最大のメリットは、企業の理念やビジョン、社風はもちろん、社長や社員の人柄や職場の雰囲気をリアルに伝えられる点にあると言えるでしょう。
さらに、動画の特性として「視聴者の記憶に残りやすい」ことが挙げられます。そのため、知名度がそれほど高くない企業でも、視聴者に覚えてもらいやすくなります。
特に中小企業は大企業に比べて知名度が低いことが多く、求職者の目に触れる機会も少ないため、企業の魅力が十分に伝わってない可能性があります。
もちろん、どんなに素敵な採用動画でも、ただ作るだけでは効果を発揮しません。求職者の目に触れ、心に届くよう、動画を起点とした採用戦略全体の設計と、動画内での見せ方の工夫も欠かせないのです。
採用コストを削減できる
採用動画は一度制作すれば繰り返し利用できるため、説明会や面接など様々な場面で活用でき、結果として採用コストの削減に繋がります。
例えば、これまでは人事担当者が一から説明していた内容を動画にまとめ、それを応募者に見てもらうことで、工数削減や説明業務の均質化を実現できます。
応募者へのアプローチがしやすい
いわゆるZ世代やミレニアル世代は、日常的にYouTubeやInstagramなどの動画コンテンツに親しんでいます。
スマホでの動画視聴が当たり前となっている世代にとって、採用動画は自然な形で企業を知るきっかけになるでしょう。
また、最近では縦型のショート動画が主流となっており、採用動画でも取り入れている企業が増えています。
さらに読む:ショート動画(縦型短尺動画)の魅力とは?
2.採用動画をより効果的に活用するには

採用動画を導入する際、そのメリットを最大限活用するためには、どのような動画を制作すれば良いのでしょうか。
ここでは効果的な動画制作のポイントを紹介します。採用動画に限らず、様々な動画制作で共通する重要なポイントもありますので、ぜひ参考にしてください。
目的を明確に設定する
どんな動画を作る際にも大切なのが、きちんとした目的設定です。「ターゲットは誰なのか」「ゴールはどこなのか」を明確にし、制作を始める前にしっかり固めておきましょう。
例えば、中途応募者をターゲットにする場合、ゴールとして「自社の風通しの良い社風を伝えたい」「企業の認知を拡大したい」といったポイントを設定することが必要です。
もしゴールを定めないまま進めてしまうと、中途応募者向けのはずが、充実した研修制度や将来性のアピールといった、新卒者が興味を持ちそうな内容になってしまう可能性もあります。
また、自社の認知拡大を狙っていたにもかかわらず、休日制度や福利厚生に焦点をあてて応募者を増やすような、当初の目的とは異なる方向に進んでしまうリスクも考えられます。
採用したいターゲットや目的に応じて、動画の構成や内容を変える必要があることを意識しましょう。
さらに読む:求職者目線を忘れない採用動画制作のポイント!
採用目的に合った構成にする
上記で設定した内容に合わせて採用動画を作るには、目的に合った構成を考えることが不可欠です。まずは職種や雇用形態に合わせた内容にすることが求められます。
例えば、営業職向けの採用動画の場合、1日のスケジュールや売上目標達成への取り組み、インセンティブ、成功事例やキャリアアップの道のりなど、その職種にふさわしい内容を盛り込みましょう。
ストーリー性を持たせる
とは言え、自社が伝えたいことをすべて詰め込んでしまうと、情報量が多過ぎて視聴者が退屈してしまう恐れがあります。
特に採用動画の場合、ターゲットが比較的若い世代であることが多いため、冗長な内容では彼らの関心を引くのは難しいでしょう。
若い世代の心を掴み、自社に興味を持ってもらうには、動画にストーリー性を持たせるのが効果的です。
例えば、社員紹介をシリーズ化して公開する、毎日の業務をドラマ仕立てで表現するなど、ターゲット層に合わせたストーリー設計を試みましょう。
尺は短めにする
現在はショート動画が主流となりつつあるため、採用動画も短い方が視聴されやすくなります。できるだけ1本の長さを、1〜3分以内に収めるよう心がけましょう。
ただし、求職者の興味や関心によっては、長尺の動画が効果的な場合もあります。自社に対して一定の関心を持っている求職者には、企業としての理念やビジョン、将来性などをしっかり伝えるために、少し長めの動画を用意するのも一つの手です。
不特定多数の人に向けて自社を知ってもらうには短い動画が有効であり、詳細を知りたいと思っている求職者には、長尺の動画を提供するのが理想的だと言えるでしょう。
リアルな職場や社員を見せる
企業が描く「理想的なイメージ」だけではなく、実際の職場の雰囲気を見せることは、求職者に信頼感を与え、企業とのミスマッチを減らすためにも非常に有効です。
具体的なシーンを見せることで、「自分がその職場で働いている姿」をイメージしやすくなります。
休憩時間やランチタイムの様子、デスク周りなど、職場の日常的な風景を盛り込むことで、求職者が企業を身近に感じられるようにするのが、リアルな映像を作るコツです。
社員の代わりにモデルを使う場合もありますが、どうしてもリアリティに欠けてしまいがちです。可能であれば、実際の社員に出演してもらえるよう交渉しましょう。
SNSが普及した現代では、企業が意図的に良く見せようとしてリアルでない職場環境を映し出してしまうと、あっという間に拡散し炎上するケースもあるので注意が必要です。
複数のメディアを使う
せっかく作った採用動画ですから、ターゲット層に届けるために、さまざまなメディアを活用しましょう。求人媒体だけでなく、自社のWebサイトやYouTube、SNSなどにも積極的に展開していくことが重要です。
各メディアにはそれぞれ利用者層に特徴があるため、複数のメディアを活用することで、より広範囲にリーチできます。
特に予算が限られていて、1本しか採用動画を制作できない場合は、SNSを活用して幅広い層に届けることで、効果を最大化する方法が考えられます。
3.採用動画で得られる4つの効果

求職者の行動を促す魅力的な採用動画を制作すると、企業にどのような効果をもたらすのでしょうか。ここでは代表的な4つの効果をご紹介します。
応募者数の増加が期待できる
採用動画を制作して、求人サイトや自社Webサイト、SNSなどに公開すれば、応募数の増加に繋がる動きを生み出せます。
特に自社の魅力や社風が伝わる動画、求職者の関心や価値観にマッチした動画であれば、視聴者の興味を引きやすく、応募意欲を高める効果が期待できるでしょう。
このように「動画ならではの訴求力」を活かすことで、より多くの求職者に「ここで働いてみたい」と感じてもらえるのではないでしょうか。
応募者の質が向上する
採用動画を通じて自社の理念やビジョンをしっかり伝えれば、企業に共感した質の高い応募者を集めやすくなります。
自社への理解が深い人材なら、仕事へのモチベーションも高いため、入社後も高いパフォーマンスを発揮し、離職率の低下にも寄与するのではないでしょうか。
採用のミスマッチを削減できる
「入社したものの、思っていたイメージと違った」といったミスマッチによる早期離職は、企業にとって大きな損失です。
採用動画で職場のリアルな状況を見せることにより、入社前に求職者が持つイメージが現実と一致し、入社後のミスマッチが減少します。結果として早期離職を防ぎ、再採用にかかるコストの削減にも繋がるのです。
ブランディング効果がある
採用動画は企業の文化や価値観、イメージを効果的に伝えるため、企業ブランドの強化が期待できます。つまり採用動画は、ブランディングツールの一つでもあるのです。
さらに自社の長所や実績、社会貢献などを具体的に紹介することで、企業のイメージアップや他社との差別化も図れるでしょう。採用活動を通じて、企業としての認知度や信頼感の向上も期待できます。
4.採用動画の最新トレンド

動画コンテンツはエンタメの一種であり、流行り廃りのスピードが非常に早いのが特徴です。むやみに流行を追いかける必要はありませんが、ある程度のトレンドを押さえておけば、若い求職者に見てもらいやすくなるのは間違いありません。
具体的に現在、採用動画において注目されているトレンドをいくつかご紹介しましょう。
ドキュメンタリー形式の動画
「ドキュメンタリー」とはフィクションを加えず「事実を伝えること」を重視した映像スタイルです。
近年、オフィスのリアルな1日を追うドラマティックな構成にしたり、1人の社員の成長や挑戦をドキュメンタリー形式で描いたりする動画が人気を呼んでいます。
ありのままの社員のひととなりや、リアルな社風を伝えることで、視聴者の共感を呼び起こしやすく、結果として企業への理解が深まる点が魅力です。
Vlog風の動画
「Vlog(ブイログ)」とはVideo blog(ビデオブログ)の略で、簡単に言えば動画を使ったブログのことです。個人的な視点で日常生活や旅行記、趣味などを紹介する動画で、近年人気のスタイルです。
これを採用動画に応用し、日常の職場風景をVlog形式で紹介することで、求職者に「働くイメージ」をしっかりと伝えられます。そして「ここで働いてみたい」「自分も仲間に入りたい」といった気持ちに繋がれば成功です。
また、社員のオフタイムの過ごし方などもVlog形式で紹介すれば、「プライベートも充実する職場」という印象を与え、ワークライフバランスを重視する世代に響く内容となるでしょう。
インタラクティブ動画
「インタラクティブ(双方向)動画」は、視聴者のアクションに応じて内容が変化する動画です。双方向のコミュニケーションが可能で、視聴者のエンゲージメントの向上が期待できます。
例えば、社員インタビューをインタラクティブな形式で提供し、求職者が興味のある項目を選べるようにする、またはオフィスツアーの動画で視聴者が自由に訪れたい場所を選べるようにするなど、視聴者が主体的に参加できる動画の実現が可能です。
また、部署や社員のコメントを、それぞれポップアップで表示するような工夫も盛り込めます。こうした体験型の動画は、視聴者に強い印象を与えるでしょう。
ビハインド動画
普段はなかなか見られない現場の裏側や、社員がリラックスしているシーンを「ビハインド・ザ・シーン動画(BTS、ビハインド動画)」として紹介すると、求職者に安心感や親近感を抱いてもらいやすくなります。オフショットや舞台裏を見せることで、企業の実態をよりリアルに感じてもらえる点が特徴です。
さらに読む:YouTubeショートのビハインド動画
5.社内で準備すべきこととは

採用動画の制作は、プロの動画制作会社に依頼することをおすすめしますが、あらかじめ社内でできる準備をしっかり整えておけば、よりスムーズに進められるでしょう。
ここでは事前に準備しておくべき項目をまとめましたので、チェックリストとしてぜひ参考にしてみてください。
採用ターゲットを定義しているか
「2.採用動画をより効果的に活用するには」の冒頭で説明した通り、動画のターゲットとゴールは事前に決めておくことが重要です。どのような人材を求めているのか、どのフェーズ(認知や理解促進など)を目的とした動画なのかなどを、あらかじめ明確にしておきましょう。
動画制作の予算を確保しているか
制作会社に依頼する場合は、予算を事前に決めておく必要があります。その金額によって、撮影方法や表現の範囲が決まるため、予算内でどのようなことが可能かをしっかり把握しておきましょう。
また、自社が持っている既存の映像や画像を活用できる場合、コストを抑えられるケースもあります。社内に使える素材があるかどうか確認しておくことも、予算管理には有効です。
さらに読む:【事例付き】動画制作にかかる費用の相場は?
インタビューや出演協力者を決めているか
採用動画に人物を登場させる際は、出演者を早めに決めておきましょう。自社社員を起用する場合でも、業務の都合や部署との調整で、スケジュールが変更になるケースもあり得ます。出演者のスケジュールは、余裕を持って調整しましょう。
もし社員の出演が難しい場合は、プロのモデルを起用する選択肢もありますが、やはりリアルさに欠ける可能性があるため、あまりおすすめはしておりません。
撮影候補日を複数確保しているか
撮影日は予備日を含め、複数日確保しておきましょう。出演する社員の体調不良や急な業務変更、さらに外での撮影では天候に左右される可能性も。予定通り撮影できない事態に備えて、余裕を持ったスケジュールを立てることが成功のカギです。
活用するメディアの選定をしているか
採用動画をどこで配信するのかも重要なポイントです。動画を公開する場所としては、WebサイトやSNS、説明会などさまざまな選択肢があります。
大切なのは求職者が自社に接触するタイミングで、知りたい情報がその手元に適切に届いているかを、きちんと見極めることです。どのような動画をどこで見せるのが効果的か、判断が難しい場合には、ぜひプロの動画制作会社に相談することをおすすめします。
納期を明確にしているか
採用動画をいつまでに、どこで公開したいのかを明確にしておくことが大切です。そこから逆算して、撮影や編集などの制作スケジュールを決めていきます。
一般的に、動画の制作期間は1〜2か月程度かかります。ここで注意したいのは、動画制作会社からの納品日と公開日が近い場合です。「納品はされたものの、手続きに時間がかかり公開予定日に間に合わなかった」といった事態を避けるため、スケジュールには余裕を持たせましょう。
さらに読む:動画ディレクターが解説!動画制作の進め方
まとめ:効果的な採用動画の実現は最初の準備段階で決まる!
今回は「どのような採用動画が求職者に”刺さる”のか」、効果的な採用動画の作り方について紹介してまいりましたが、いかがだったでしょうか。
採用動画は、適切に活用すれば企業の魅力を的確に伝え、求職者の応募意欲を高める強力なツールとなります。
導入する目的を明確にし、その内容に合った構成を考えるのはもちろん、現代のトレンドも意識しながら制作することが重要です。
これは採用動画に限らず、動画全般に言えることですが、「どこで」「どう使うか」によってその成果は劇的に変わります。自社で判断が難しい場合は、プロの動画制作会社に相談することをおすすめします。
本コラムで紹介した内容を参考に、人材採用の課題を解決する「動画を活用した採用戦略」を構築してみてはいかがでしょうか。
バドインターナショナルでは、採用動画の制作はもちろん、採用に関する各種ツールなどの制作も承っています。最近主流となっている縦型動画にも対応可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。