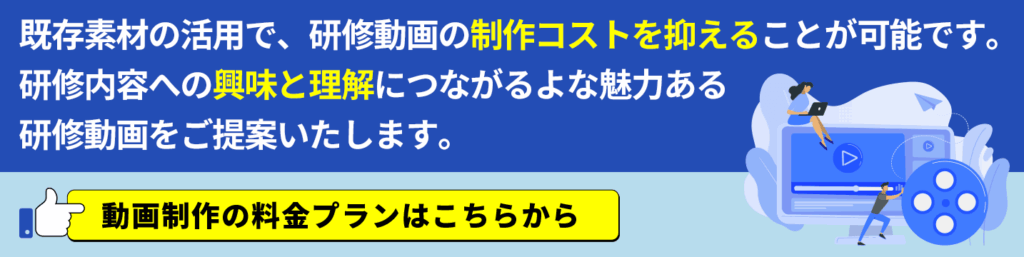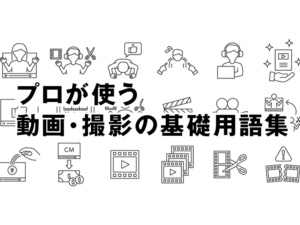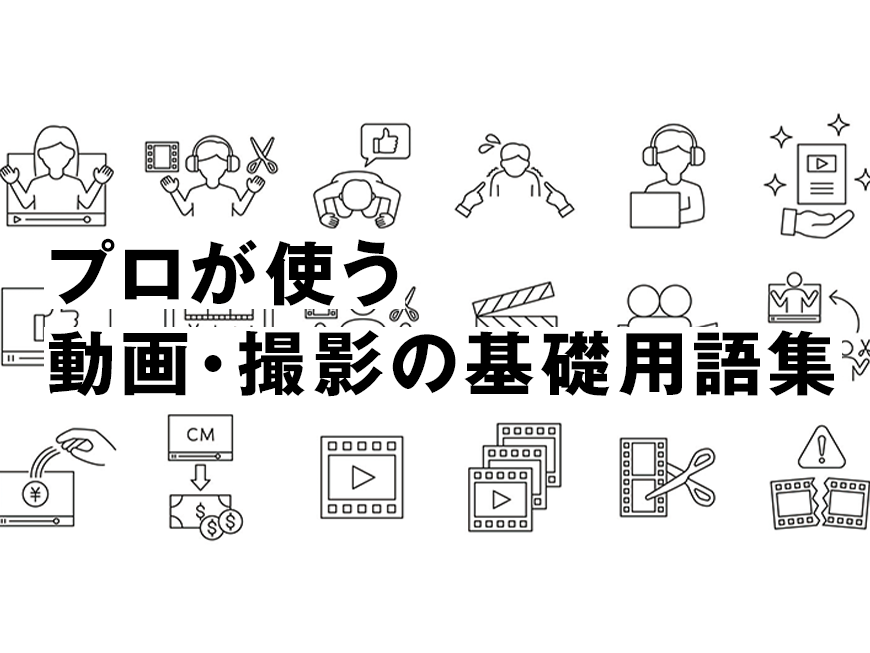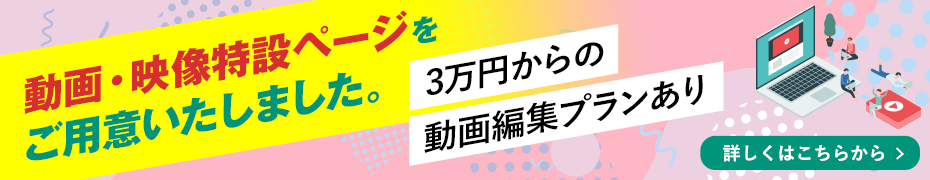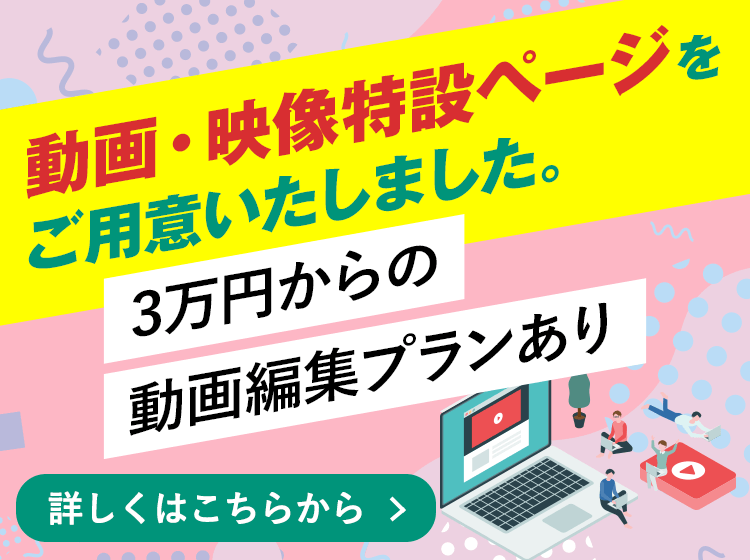近年、企業や組織において、研修動画を活用した教育方法の導入が進んでいます。日時を指定して1か所に講師と社員を集めるような、従来の物理的な集合研修とは異なり、動画なら時間や場所にとらわれず、従業員が自分のペースで学習することが可能になります。
しかし「動画による研修」と聞くと、その有効性に疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
・研修動画にはどのような効果が期待できるのか
・動画を使った研修のメリットは何なのか
・どのような研修動画を作れば良いのか
本記事ではこういった疑問にお答えし、研修動画の導入がもたらすメリットや成功させるためのコツ、活用事例まで詳しく解説していきます。
研修動画の導入を考えている方、効果的な研修方法を探している方は、ぜひ最後までご覧ください。
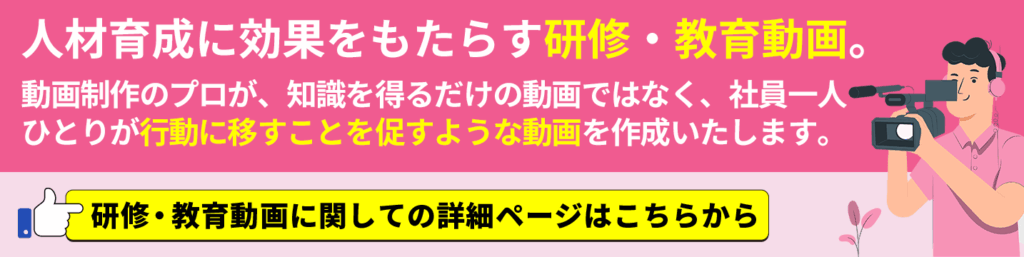
目次
1.企業研修における研修動画の位置づけ

そもそも「研修動画」とはどういったものなのでしょうか。「なんとなく聞いた覚えはあるけれど、実際に研修動画を見たことがない」いう方もいらっしゃると思います。
そこでまず、その定義や背景、企業が抱える課題などから、研修動画について紐解いていきたいと思います。
そもそも研修動画とは?
研修動画とは、企業が提供する教育コンテンツの一部として、社員教育や企業研修として制作される動画教材のことです。
企業理念やビジョン、業務内容、コンプライアンスなど、幅広いテーマを扱えるのが特徴です。主に自社の社員に知識やスキルを伝え、企業文化を浸透させ、ノウハウを習得させることを目的としています。
研修に動画を用いる企業が増えている
かつて企業の研修と言えば、まず日時と場所を決めて、1か所に社員や講師を集めて行う集合研修がメインでした。しかし人手不足やリモートワークの普及、多様な人材育成などのニーズにより、現在では研修動画の導入が進んでいます。
社員の教育・研修は、スキルアップによる生産性向上や組織全体の競争力強化、離職の防止などに繋がる重要なものです。社員本人にとっても、雇用する企業にとっても必要不可欠なため、より効率的で柔軟な形態へのシフトが進んでいます。
特に動画慣れした世代の若い社員にとって、研修動画を使って行われる教育は、より身近で馴染みやすい学習方法だと言えるでしょう。
集合研修の制約を解消する研修動画
前述の通り、従来型の集合研修には時間や場所の制約があり、その調整にかかるコストも馬鹿になりません。また担当する講師の教え方により、研修・教育の内容にムラが生じることも。そうなると、受講者の理解度にばらつきが生じる可能性も出てきます。
研修動画を上手に活用すれば、こういった制約やコスト面での課題を解決できるだけでなく、学習効果を高めることにも繋がります。
2.研修動画を導入する5つのメリット

研修動画には、研修を提供する企業側と受講する社員側、新入社員や中途社員とベテラン社員、あるいは受講者の役職などに関係なく、それぞれの立場で得られるメリットがあります。ここではそのうち、代表的なメリットを5つご紹介しましょう。
コストの削減に繋がる
研修動画を活用すると、経済的なコストだけではなく、時間的・肉体的・精神的な負担にかかるコストも削減されます。
もちろん、動画制作にかかる費用は最初に発生します。しかし動画は一度作ってしまいさえすれば、繰り返し利用することが可能です。つまり長期的に見た場合、経済的なコストが削減できるケースがあるのです。
集合研修では、特に参加する人数が多い場合、会場をレンタルする必要も生じます。その費用や設営・運営にかかるリソースも、研修動画の導入で削減できる可能性も。
動画なら決まった場所や時間にとらわれることなく、好きな時間にリラックスして見られるため、受講者の精神的なコストの軽減も可能です。
さらに毎回、開催する側・講師として出席する側・受講する側それぞれの調整も不要なので、それにかかる負担も少なくて済みます。
さらに読む:動画制作会社の見積書を大公開!
時間と場所の制約がない
ここまでご説明してきたように、研修動画ならいつでもどこでも、場所や時間に関係なく、受講者が自分の好きな時間や場所で視聴できます。つまり、受講する社員が、自分のペースで学習を進められるのです。
会場となる場所を確保し、講師のスケジュールを確認して、時間を決めて開催する従来の物理的な集合研修との決定的な違いは、この「自分のペースで」という点にあると言えるでしょう。
研修内容の一貫性を確保できる
ある研修で同僚が教わった内容を、自分が受けた同じ研修では教えてもらえなかった。こんな経験はないでしょうか。
同じテーマで同じ教材を使っていても、担当する講師が違ったり、時間が押してしまったりすると、研修の内容にムラが生じる可能性があります。
その点、研修動画ならすべての受講者が同じ動画を見ますので、環境や講師のスキルに左右されることなく、均質な研修内容を提供できるのです。
企業文化の醸成・社員エンゲージメントに貢献する
受講者が興味を持って研修動画を見てくれれば、その後の学習意欲も高まり、社員としての自己成長の促進にも繋がるでしょう。結果として、社員エンゲージメント向上への貢献も期待できます。
さらに企業理念やビジョン、価値観などを共有することで、企業の一員としての自覚を促す効果も期待できます。醸成を重ねてきた企業文化に積極的に参加して、活躍してもらうきっかけにもなるのではないでしょうか。
もちろんそのためには、受講者が最後まで飽きずに視聴でき、社員としての参加意欲に繋がるような、魅力ある研修動画の制作が必須なのは言うまでもありません。
学習効果の向上が期待できる
特に新入社員や中途社員の研修の際、会社や業務に早く馴染んでもらうためにも、視覚と聴覚を同時に用いる研修動画は有効です。
動画にはテキストベースの教材よりもはるかに情報量が多いという特性があり、目と耳から情報をインプットすることで、学習内容をより効果的に理解しやすくなるからです。
また、受講中にうっかり講師の話を聞き逃してしまったり、理解できない箇所が出てきたりすることもあるでしょう。その際も動画なら何度でも戻して見られるため、受講生自身のペースや理解度に合わせて研修を進めていけます。
この「繰り返し視聴できる」という点は、内容への理解をより一層深めるためにも、非常に重要なポイントだと言えるでしょう。
3.研修動画のデメリットとは?

ここまで研修動画のメリットを説明してきましたが、もちろんデメリットも存在します。自社に導入する際には、メリットとデメリットの両方を理解した上で、検討するのがおすすめです。
もし自社には合わないという結論に達した場合には、無理に研修動画を作らずに、集合研修やテキストベースの教材などでの代用も検討しましょう。
講師と受講生のコミュニケーションが取りにくい
対面で受ける研修なら、その場でその時に質問や意見ができる、リアルタイムでのコミュニケーションが可能です。
その一方、研修動画は受講者がそれぞれ好きな時間や場所で視聴するため、その場で疑問が湧いた際に、リアルタイムでフィードバックをもらうのは難しいのが実情です。
視聴後に各自で質問をまとめ、講師に後日回答してもらうといった対応は可能かもしれません。しかし動画の視聴を進めていくうちに、質問したかった内容自体を忘れたり、「後でいいや」と放置したりしがちです。
そうなると、自分が「何がわからなかったのか?」すら思い出せないまま、業務に取り組むことになる可能性も。
リアルタイムでのコミュニケーションができない分、疑問が出たらその場でメモする習慣をつけるなど、受講者側に能動的な工夫が求められます。
モチベーションが続かない恐れがある
前項のコニュニケーションが難しいことにも関連しますが、受動的に長時間視聴していると注意力が散漫になり、受講者のモチベーションが低下する可能性があります。
結果的に「視聴はしたけれど何も覚えていない」という、その後の業務にも支障を来す事態になるケースもあり得ます。
最後まで集中して見てもらうには、視聴者には飽きさせない工夫が欠かせません。例えばゲーム要素を取り入れてみる、インタラクティブな動画にするなど、何かしら視聴者のアクションを促す展開を取り入れた動画にしてみましょう。
内容をこまめに変更できない
研修内容に変更さえなければ、長期的に活用できるのが研修動画の理想であり、メリットでもあります。
その一方で、研修内容が毎回のように変わったり、細かい修正が毎回入ったりする場合は、その都度動画を修正しなければなりません。そうなると、研修の度に修正内容の確認を行わなければならず、手間やコストがかかってしまいます。
研修動画を制作する際は、研修内容に変更が出にくいコンテンツを選んだり、後から差し替えがしやすい構成にしたりといった対策が必要です。
4.成功する研修動画制作のコツ

これまでお話ししてきたように、研修動画の成功のカギは、動画の長さやテンポ、視覚的な工夫など、受講者が飽きずに学習できる要素を盛り込むことだと言えます。また、インタラクティブな要素を取り入れるなど、受講者が積極的に参加せざるを得ない構成にするのも、集中力やモチベーションを維持する上で大切です。
つまり、受講者の学習効果を高めるには、動画の構成や内容、そして配信方法まで、あらゆる面で工夫が必要なのです。ここでは、研修動画の制作を成功させるためのコツを、4つの観点から解説していきましょう。
動画の目的を明確にする
研修動画を制作する際、最初に行うべきなのは「目的の明確化」です。動画の目的を明確にし、ターゲットとなる社員にどのような知識やスキルを習得させたいかを、まず明らかにしなければなりません。
「新入社員の教育」「既存社員のスキルアップ」「新製品の説明」など、目的によって動画の内容や構成は大きく変わります。最初に目的をはっきりさせることで、受講者に伝えるべき情報が整理され、効果的な動画制作が可能になります。
内容に合ったスタイルの動画にする
また、動画のスタイルを考えることも大切です。目的に合った形式で制作すれば、より効果的な研修が実現します。動画のスタイルには、以下のようなものがあります。
講義スタイル
実際に講師が出演して、受講者に向かって講義を行う形式の動画です。新たに撮影したもののほか、集合研修の様子を録画した映像も活用できます。
マニュアルスタイル
業務の内容や作業手順、機器の操作方法などを説明するのに向いている動画です。紙のマニュアルでは伝わりにくい内容も、動画にすることでわかりやすくなります。
ドキュメンタリースタイル
実際に仕事をしているシーンなどを撮影し、ドキュメンタリーのような形式にまとめた動画です。受講者に社内の雰囲気や業務内容を伝える動画です。
わかりやすくまとまった動画構成にする
研修動画は、視聴する受講者に内容を理解してもらうことが最優先です。最初から専門用語を使うのは避け、誰にでも理解できる平易な言葉で説明することがポイントです。
テロップや図解、イラストなどの視覚的要素を画面にうまく取り入れることで、情報を直感的に伝えられるのも、動画ならではの魅力です。特に重要な事項は、テロップの色やサイズ、フォントを変えるなどの工夫で強調し、視聴者の理解を深めましょう。
また、先述の通り、長時間の動画は集中力が途切れやすいため、複数のチャプターに分割したり、テーマごとに動画を分けたりすることで、短時間で視聴できる工夫も大切です。視聴者の集中力を維持するには、1本の動画を10分以内に収めるのが効果的です。
質の高い動画にする
社内での研修用だからといっていい加減に作ってしまうと、質の良くない動画になり、結局使い道が限られたり、後で作り直す必要が出てきたりする場合があります。
例えば音声や話し方一つとっても、聞きやすいプロのナレーターや専門の講師を起用したり、高精度なAI音声を利用したりなど、工夫するところは多くあります。もちろん画質や画面構成にもこだわって、見やすい動画を作りましょう。
また、研修動画は一度作成して終わりではなく、定期的に内容を見直して、最新の情報やフィードバックを反映させる必要があります。常に質の高い研修を提供するためにも、この点を怠らないようにしましょう。
5.効果的な研修動画の活用事例

ここまで説明してきたように、研修動画は従来の集団研修に比べ、時間や場所にとらわれず、効率的に学習できるというメリットがあります。そのため、最近では企業や組織の教育手法として、効果的に活用されるようになりました。
ここでは、そんな研修動画の活用事例を3つご紹介します。
新卒・中途採用の社員向け研修での活用
新入社員のためのオリエンテーションを研修動画にすることで、会社概要や業務内容、職場のルールをわかりやすく説明できます。動画を視聴してもらうだけで、新入社員の会社への理解が深まり、研修の効率化が図れます。
一人ひとりの新入社員に対し、各部署で個別に説明する手間が省けるだけでなく、情報のばらつきを防ぐことも可能です。また、動画は繰り返し視聴できるため、新入社員に自分に合ったペースで理解を深めてもらえます。
新入社員の早期戦力化には、基礎的な業務知識や社内文化の理解が不可欠です。研修動画はこういった基本的な内容を視覚的に、かつ効率的に伝える手段として効果的です。
スキルアップ研修での活用
実務スキルや専門知識を学ぶ研修動画を活用すれば、既存社員のスキルアップの促進が図れます。動画を通じて専門的な知識や技術を習得できるだけでなく、実際の業務でどのように活用するかを学習することも可能です。
例えば営業担当者のスキルアップを図るには、営業の場で起こりうる、様々な場面のロールプレイを収録した動画が有効です。多様なケースを記録し共有することで、成功事例からはもちろん、課題を残した事例からも多くを学べるのではないでしょうか。
コンプライアンス研修での活用
近年はコンプライアンスが厳しくなり、企業にとっても業務を行っていく上で、その理解や取り組みの重要性が高まっています。
法令遵守や社会的規範、企業倫理といった難しい内容も、動画で学べば理解しやすく、コンプライアンス違反の防止に繋がるでしょう。
特にハラスメント防止や情報セキュリティといったの重要なテーマを扱う際は、動画の中で具体的な事例を示すことで、より理解が深まり、社員の意識を高める効果が期待できます。
まとめ:研修動画を活用して効果的な社員教育を
今回は研修動画の有効性について解説してまいりました。企業の規模にかかわらず、研修はいつの時代も必要であり、業務の中で繰り返されるものです。研修動画の需要は、今後はより増えていくのではないでしょうか。
社員数が多い企業の場合、研修内容の平準化や、同じ説明の繰り返しが求められます。社員数が少ない企業なら、新入社員の研修に割くスタッフの確保が難しいこともあるでしょう。研修動画を一回作ってしまいさえすれば、こういった課題を解決することが可能です。
ただし、社内用だからといって適当な動画にすると、視聴者にとってはつまらない、集中力が続かないものになりがちです。そうなると研修動画としては意味のない、学習効果が期待できない動画になってしまう恐れもあります。
自社にある程度のクオリティの動画を制作できる人材がいない場合は、動画制作会社に依頼することで、受講者が飽きない構成を工夫してもらえます。長期的に活用していくのであれば、やはり動画制作のプロにお願いするのがおすすめです。
さらに読む:失敗しない制作会社の選び方
バドインターナショナルは、企画の段階から参加させていただき、受講者がしっかりと内容を理解できる研修動画・教育動画をご提案いたします。
イラストなどを用いたアニメーション動画から、実際に講師が出演する実写動画まで、幅広い対応が可能です。講師の撮影を弊社のスタジオで行うことで、コスト面でも大きなメリットも得られます。
研修・教育動画の制作をお考えなら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。